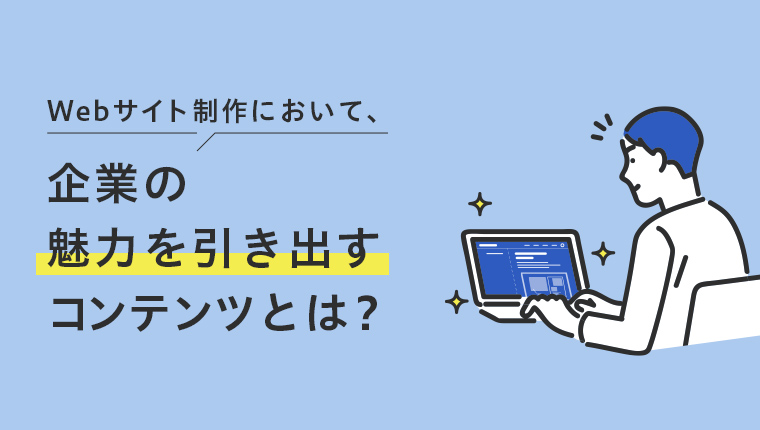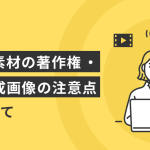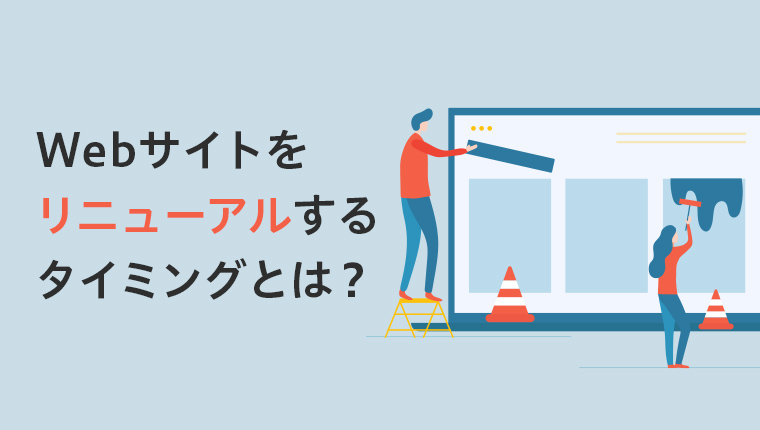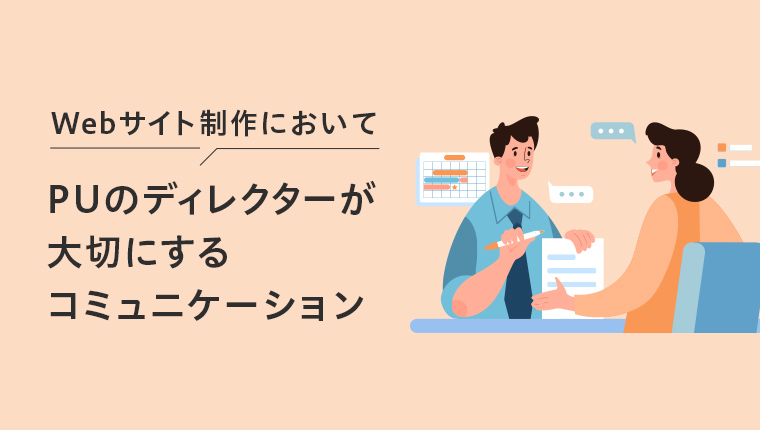ポテンシャルユナイテッド(以下、略:PU)のパーパスは「企業と顧客のベストマッチを創出するために、企業の魅力を最大限引き出し、広げる」こと。そのためには、最適なコンテンツを企画・提案し、それを確実にカタチにして発信する力が求められます。
本記事ではPUのディレクターが「どのようなコンテンツが、どのような効果をもたらすのか」について、具体例を交えてご紹介します。
CONTENTS
企業Webサイトの基本構成
企業Webサイトにとって最低限掲載が必要なコンテンツはおおよそ固定されておりますが、それだけでは企業の個性や強みを十分に伝えきれないケースも少なくありません。
外部の会社として、お客様のアイデンティティがどういったものなのか、お客様の方では、当たり前のことで気づかれていない、他社にはない素晴らしいところがどこなのか、思い、姿勢、これまでの取り組み、様々な視点で客観的に俯瞰して捉えることで、より一層、企業の魅力を引き出し、ユーザーに伝えることができます。
最後は、お客様の方から、「ほんまやなぁ~」っと言われた瞬間が、何とも言えない達成感となります。
企業の魅力を引き出すコンテンツ事例
◾️映像資産を活かす「メディアライブラリー」
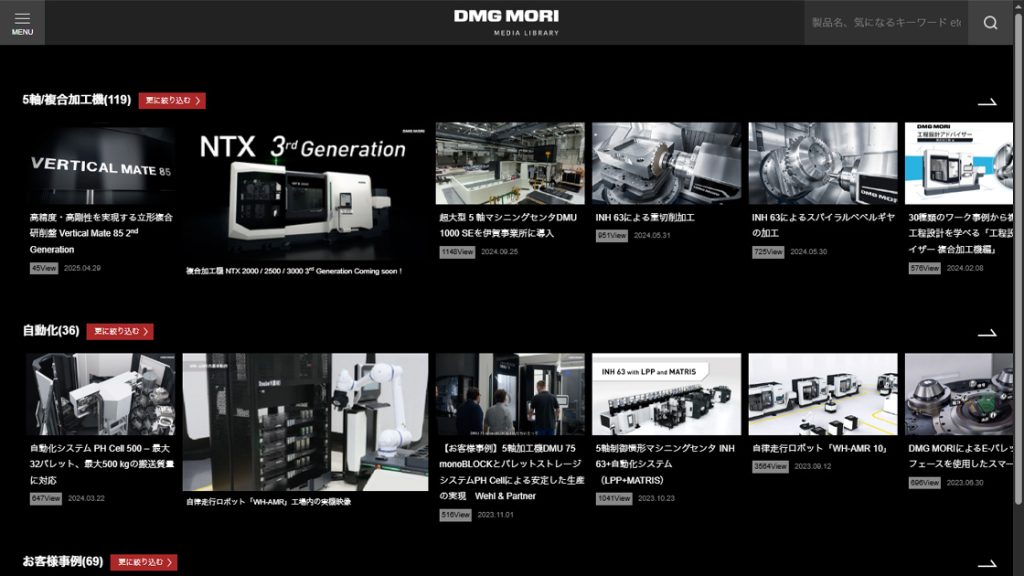
https://www.dmgmori.co.jp/movie_library/
映像コンテンツが豊富な企業におすすめなのが、独自の「メディアライブラリー」です。YouTubeに動画をアップロードしていても、検索機能が限定的なため、ユーザーが見たい専門的な動画をすぐに見つけるのは難しい場合があります。企業Webサイト内に、カテゴリやキーワードで整理された検索機能付きライブラリーを設けることで、視聴者の利便性が高まり、閲覧数の向上が期待できます。
◾️内観を見せる「パノラマビュー」

https://www.omm.co.jp/exhibition/exhibition/mainhall.html
施設の魅力を効果的に伝える手段として、360度パノラマビューの導入がおすすめです。特に、工場やホールなど「空間そのもの」が強みとなる施設では、写真や動画だけでは伝えきれない臨場感をユーザーに提供できます。3DCGやパースを活用する方法もありますが、制作には高額な費用や時間がかかるのが難点。その点、RICOH360のカメラとクラウドサービスを組み合わせることで、リーズナブルかつスピーディーに導入できます。施設紹介ページや採用コンテンツ、営業資料などへの活用も可能で、コストパフォーマンスの高いソリューションです。


https://www.ricoh360.com/ja/theta/
◾️事業内容をストーリーに落とし込んだコンテンツ

https://www.kawaidenki.co.jp/service/story.html
分かりづらい事業内容をストーリー仕立てにすることでイメージを湧きやすく
企業の中には、一般的にはなじみがなく、事業内容が伝わりにくいケースも多くあります。
そんなときに有効なのが、事業内容をストーリー仕立てで紹介するコンテンツです。
「誰が・どんな課題を抱え・どう解決されたのか」という流れで伝えることで、ユーザーは実際の活用シーンをイメージしやすくなり、親近感や理解が深まります。結果として、お問い合わせ数の増加や採用活動への好影響も期待できます。
また、守秘義務の関係で実際の導入事例をそのまま公開できない場合でも、実話をベースにしたフィクションとして展開すれば、企業の強みや提供価値を伝えることは十分可能です。
◾️見せ方にひと工夫したコンテンツ
よくあるコンテンツも切り口一つで、キラーコンテンツに
よくあるコンテンツでも、「見せ方」次第で一気に魅力が増し、ユーザーの心をつかむ“キラーコンテンツ”になることがあります。
たとえば、同じ内容でもタイトルの付け方やコンテンツの切り口を工夫することで、より多くの人の興味を引き、閲覧数の増加が期待できます。
このとき重要なのは、コンテンツの中身(訴求ポイント)から逸れすぎないこと。奇をてらいすぎず、本質に沿った「ひと工夫」が、効果的な引き出し方につながります。
例1|北洞株式会社

https://www.kitahora.com/concierge
京都に本社を構える北洞株式会社は、糸の卸売業を営む老舗企業。
その強みは、用途や素材に合わせて最適な糸を提案する「糸のコンシェルジュ」の存在です。
導入事例コンテンツに「必殺糸事人(ひっさついとじん)」というユニークなタイトルを設定されており、このネーミングによって、読み手の興味を引くだけでなく、登場する職人や企業の“モノづくりへのこだわり”を物語として伝えることができます。
その物語のなかに北洞の糸が登場することで、製品価値も自然と高まり、より深い理解と共感が生まれています。
例2|KTX株式会社
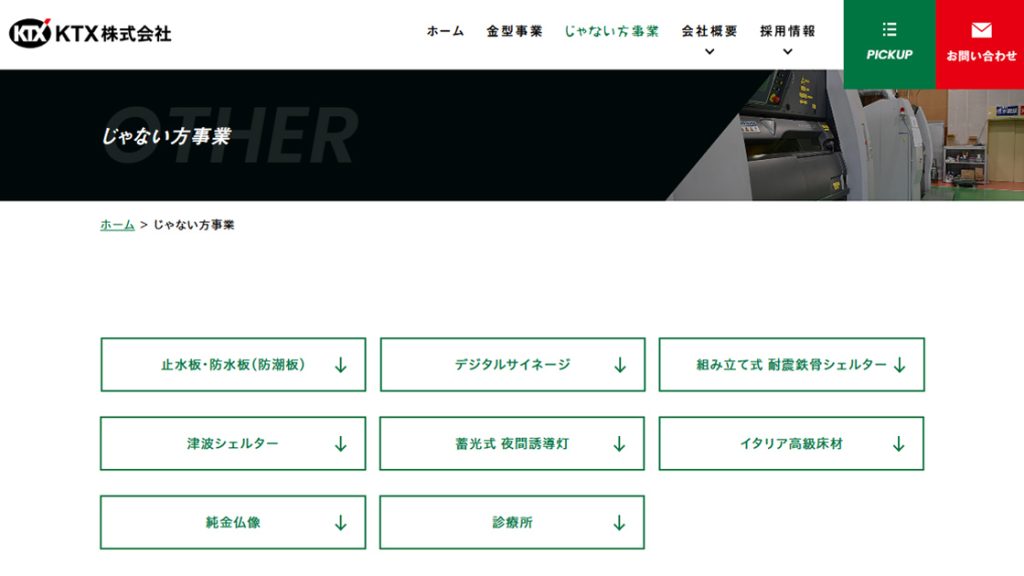
https://www.ktx.co.jp/other/
KTX株式会社は、世界的にも高い評価を受ける電気鋳造技術を持つ金型メーカーです。
そんな同社が新たに立ち上げたのが、既存の事業とはまったく異なる領域に挑戦した新規事業「じゃない方事業」。
新たな市場を創造するために立ち上げた事業を「楽しく」「本気」で取り組むため、ユーザーに覚えてもらいやすい名称に設定しています。
フォントやビジュアルも既存ページと変えることで、“なんだろう?”と思わず見てしまう仕掛けが、認知やブランディングの入り口として機能しています。
◾️「特長」に特化したコンテンツ
サービスサイトだけでなくコーポレートサイトでも「特⻑」
「特長」コンテンツは、サービスサイトでは定番の構成ですが、コーポレートサイトでも十分に効果を発揮します。
とくに、提供価値が目に見えづらい業種やサービスにおいては、「特長」を打ち出すことで、企業の強みやこだわりを具体的に伝えることができます。
課題を切り口に構成することで、ユーザーが自分ごととして読み進めやすくなり、問い合わせや共感につながるケースも少なくありません。
例|オーツー・パートナーズ株式会社

https://www.o2-inc.com/feature/
製造業に特化したコンサルティングやプロジェクトマネジメントを提供する専門家集団、オーツー・パートナーズのコーポレートサイトでは、「特長」コンテンツを効果的に活用しています。一般的にイメージしづらいコンサルタント業において、サービスサイトのように「特長」を明示することで、提供価値を分かりやすく表現。
「どんな課題に対して、どのような支援ができるのか」を軸に構成しているため、ユーザーは自らの悩みと照らし合わせながら読み進めることができ、理解促進と問い合わせ意欲の向上が期待できます。
◾️パーパスを伝えるために工夫したコンテンツ
世界的なトレンドとして、「サステナビリティ(持続可能性)」という大義名分のもと、企業が自らの存在価値を定義し、その価値に基づいて企業活動を再構築・発信する動きが広がっています。
その中で注目されているのが、企業の存在意義を示す「パーパス」。現在ではこのパーパスを軸とした表現設計や情報構造の見直しが、企業のWebサイトにも求められるようになってきました。
コーポレートサイトのリニューアルにおいても、単なるデザイン刷新ではなく、企業の“ありたい姿”を軸に据えた情報設計が重要になってきています。
例1|日本たばこ産業株式会社(JT)コーポレートサイト

https://www.jti.co.jp/cw/kokoro-note/index.html
たばこ事業の印象が強い企業ですが、実は複数の事業を展開しており、社会貢献活動にも積極的に取り組んでいます。コーポレートサイトでは、掲げているパーパス「心の豊かさを、もっと。」を軸に、JTという企業の在り方や価値観がユーザーに自然と伝わる構成が工夫されています。
注目コンテンツ|こころノート
その中でも注目コンテンツは、「こころノート」。JTが実際に行っているさまざまなアクションを記事形式で紹介することで、パーパスを“言葉”としてではなく、“行動”としてユーザーに届けています。
訪問者が当初の目的(IR情報や事業情報の閲覧など)を果たした後に、このコンテンツに触れることで、企業に対する好意や共感が醸成されるよう設計されており、結果としてセッション数が3.3倍に増加し、パーパスを軸に据えた情報設計の好事例と言えます。
例2|コクヨ株式会社

https://brand.kokuyo.co.jp/
「コクヨ=文具メーカー」という印象が強く残るなかで、掲げているパーパス「ワクワクする未来のワークとライフをヨコクする。」を軸に文具にとどまらない多角的な事業や、これからの働き方・暮らし方に向けた挑戦を伝えるべく生まれたのが、注目コンテンツ「コクヨのヨコク」です。
注目コンテンツ|コクヨのヨコク
このコンテンツでは、「すべての人がワクワクし、クリエイティブに生きる未来」を実現するための意志や挑戦、実験的な取り組みが、まるで“動くノートパッド”のようなビジュアルと構成で展開されています。
また、CMや販促物とも世界観を統一しており、ユーザーがどのタッチポイントでもコクヨの目指す“ワクワク感”を自然と体感できるデザイン・トンマナが徹底されています。
その結果として、社内におけるパーパスへの共感度が20%以上向上したほか、就職・転職意向が6%アップ、学生のサービス理解度が13%アップするなど、ブランド認知やインナーブランディングへの波及効果も表れいたそうです。
企業のパーパスを、言葉ではなく体験として届ける設計が功を奏した好事例といえるでしょう。
◾️お問い合わせのハードルを下げるコンテンツ
制作実績でもブログでもない。依頼〜納品までの流れを時系列で紹介

https://www.studio-csa.com/report/
制作実績やブログといった一般的なコンテンツではなく、「依頼〜納品までの流れ」を時系列で紹介することにより、お問い合わせへのハードルを下げているコンテンツの事例です。依頼(お問い合わせ)から納品に至るまでの一連の流れを、営業マンの視点で紹介しています。打ち合わせでのやり取りや制作過程での試行錯誤、クライアントとのコミュニケーションを日記のように綴ることで、企業がクライアントに対してどれだけ親身に取り組んでいるかが伝わります。
その結果、サイト訪問者は「一度相談してみようかな」と感じやすくなり、問い合わせに対する敷居が低くなります。このようなコンテンツは、信頼感を醸成し、より多くの潜在的な顧客に「まずは話を聞いてみよう」という気持ちを促す効果があります。
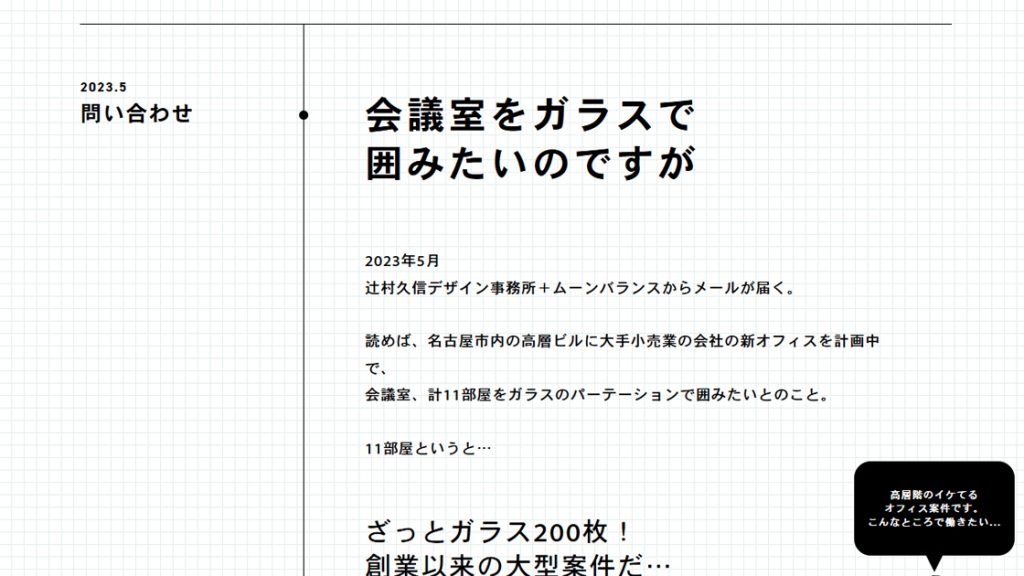
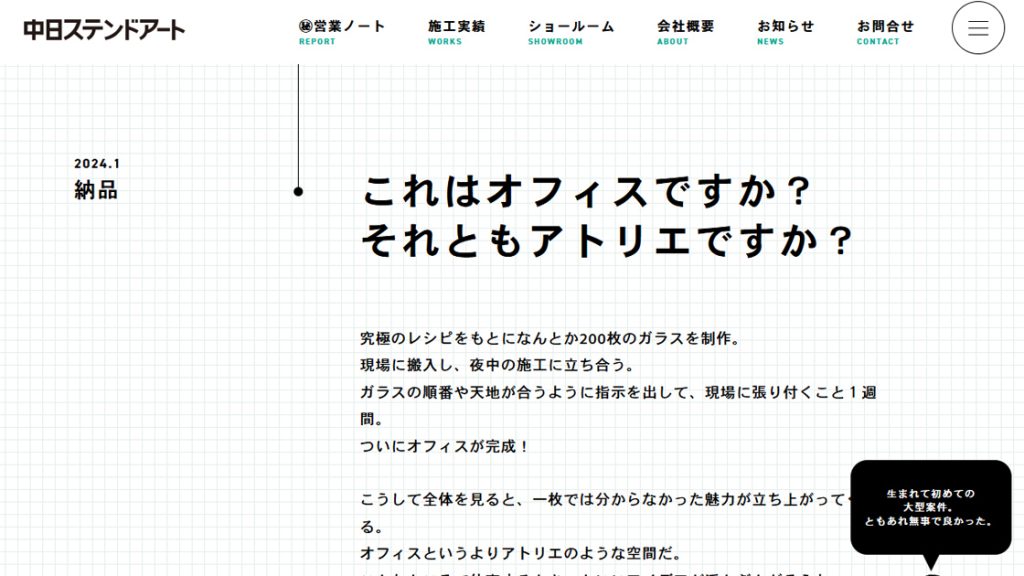
◾️思いやりが伝わるスローガンを紹介したコンテンツ
採用サイトではないけれど…一社員の未来予想図をあえて掲載

https://matsushitagumi.com/game/
採用サイトではなくコーポレートサイト内であえて一社員の未来予想図を公開しているコンテンツです。
こちらの企業は「ワーク イン ライフ」というスローガンを掲げています。このコンテンツでは新入社員のキャリアプランやライフプランを人生ゲーム風のイラストで紹介しており、視覚的にも楽しさと親近感を与えます。採用サイトによく見られるコンテンツではありますが、あえてコーポレートサイトに掲載することで、企業が「働く人を大切にしている」といったメッセージを強く印象づけています。
このような思いやりのあるアプローチは、企業文化や価値観を自然に伝え、サイト訪問者に企業の温かみや人間性を感じさせます。採用を意識したコンテンツとしても、間接的に潜在的な求職者にアプローチできる効果があります。
まとめ
企業の魅力を最大限に引き出すには、単に情報を並べるだけでなく、「誰に、何を、どのように伝えるか」という視点が欠かせません。今回ご紹介した事例のように、目的や伝えたい価値に応じてコンテンツの形式や見せ方を工夫することで、ユーザーの共感や信頼をより確かなものにすることが可能です。
PUでは、企業のパーパスやビジョンを丁寧に汲み取り、最適なコンテンツの企画・制作・発信までを一貫してご支援いたします。
「企業と顧客のベストマッチを創出する」——そのためのコンテンツづくりに、私たちは真摯に取り組んでいます。